中古から新築アパートへの方向転換
2024年2月頃、私は中古アパートの検討から方向転換し、新築アパートの情報収集を始めました。
特に建築条件付きの案件や、大手ハウスメーカーが手掛ける新築アパートに関心を持ち、複数社へ資料請求を行いました。
大手ハウスメーカーへの資料請求と印象
5社ほどに資料請求を行い、そのうち数社から営業担当者と直接会話しました。
性能やデザイン面では魅力的な物件が多かったものの、コスト面では予想以上に高く、元々土地を所有している地主層がターゲットであることが明確でした。
最初から期待をしていた訳ではないのですが、これは私のような一般会社員投資家にとっては、かなりハードルが高い条件です。
建築費高騰の実感と背景

私自身、本業で建売戸建ての開発に携わってきたため、ウッドショックや人手不足による建築費高騰は理解していました。
しかし、実際に提示された数字は想定を超えるものでした。
余談ですが、コロナの影響でリモートワークが普及し、部屋数を重視する実需ターゲットのおかげで戸建市場では高コストでも成り立っていた時期もありました。(現在の戸建市況は再び厳しくなってきています。)
実際の建築条件付き案件の価格感
提示された案件の一例として、JR中央線の快速停車駅から徒歩10分弱の立地にある物件があります。
販売価格は約3.6億円、想定利回りは4.3%という内容でした。
他にも東京、神奈川での事例を紹介してもらいましたが、いずれも土地と建物を合わせた総額が2〜3億円、利回り4〜5%という水準で、一般会社員が購入対象とするには非現実的です。
利回りから見える業者利益と自作の可能性
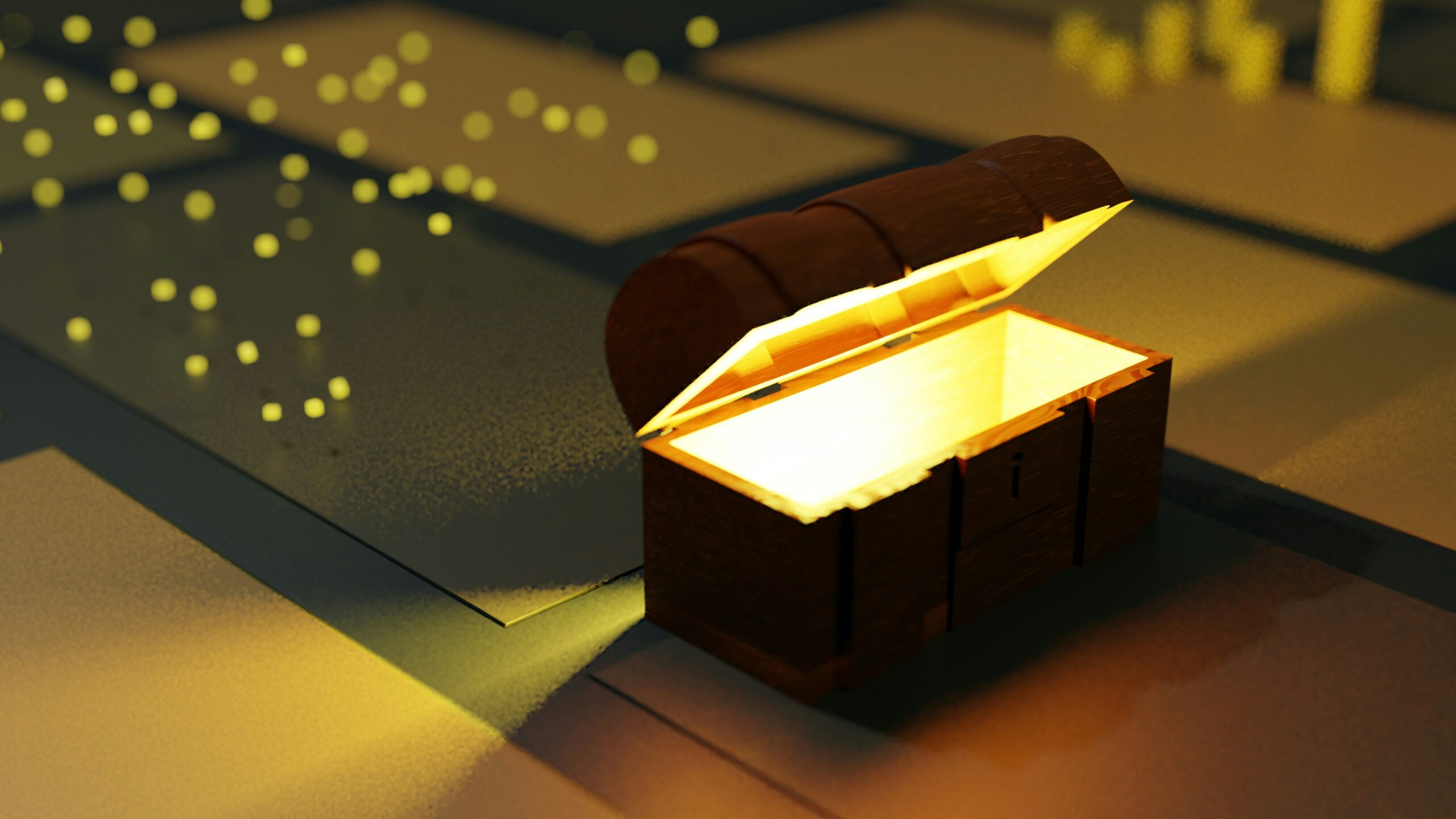
この利回りでも購入者がいる事実には驚きました。
ハウスメーカーの利益率を30%程度と仮定すると、業者利益を除いた状態では利回り6%前後の物件が成立している計算になります。
エリア選定や建物仕様を工夫すれば、新築でも利回り7%程度のアパートを自ら企画できる可能性が見えてくることに気が付きました。
資産形成を目的とした新築アパート業者の調査
次のステップとして、会社員投資家向けに新築アパートを販売している業者を調査しました。
彼らが選定しているエリア、ターゲット層、建物仕様、そして販売価格帯などの情報を収集することで、自分の投資戦略に活かすことを目指しました。
出口戦略を見据えた検討の重要性

最終的には、アパートを運営した後の出口戦略も重要です。
どのような物件が売却市場で評価されるのか、購入者層が重視する条件は何かを把握することで、長期的な資産形成において優位に立つことができます。
後編では、こうして得られた情報をもとに、具体的な業者比較や案件検討の詳細についてお伝えします。



コメント